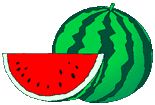 ラル達とスイカ ラル達とスイカ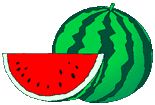 |
フレイス村の早朝、漁に出ようとラルが家の戸を開けると、そこには大きな西瓜がごろり、と転がっていた。 「あっ!凄い、大きなスイカ!(この世界にスイカは・・・あってもおかしくないかな、と思いまして)」 と見送りのために出てきたリースが嬉しそうな声を上げる。 「一体誰が?」 「・・・・わからないわ。でも、怪しいものじゃないわ。私にはわかるの。井戸で冷たく冷やしておくね。ラルが戻ってきたらすぐに食べられるように。」 リースは一度かがんでスイカを腕に抱え・・・スイカを見つめてにっこり微笑んだ。 「どうしたんだい。」 「あのね、・・・このスイカ、ラルが赤ちゃんのときと同じくらいの重さなの。」 そんな昔のことをよく覚えているなぁとラルは感心したが、よく考えてみれば、この精霊の心の中には何百年も昔に生きた魂たちがひっそり生きていて、そのときの記憶も持っていたのだと思い出した。 「人間って不思議ね。こんなに小さかったのに、ラルはどんどん大きくなって、私を追い越しちゃった。」 「俺が小さなままだった方が良かった?」 リースは首を横に振った。 「あのね、赤ちゃんが欲しいの。私とラルの。そしたらこうしてギュッと抱きしめるの。」 スイカを抱くリースを見てラルはこんこんと咳をし、真面目な顔をした。 「リース。僕はね、リースさえ居ればいいよ。」 リースはきょとんとし、くすっと笑った。 「だったらラルのこと、昔みたいに抱き上げてもいい?」 そんなこと、できるはず、と言いかけて、ラルはリースにとってはそれが造作もないことを思い出した。スイカを置いたリースはひょいと片腕でラルを抱き上げる。 「ば、馬鹿!下ろせよ!これから漁に出るんだぞ!」 「だったら船着場までこのまま駆けていってあげる!」 「こんなの見られたら、村のみんなに怪しまれるだろ!」 「それでもいいよ?」 「俺は嫌だ!」 リースはラルを下ろすと笑い声をあげながら船着場へと下っていった。ラルはスイカを一瞥し、駆け下りていくリースを見て呟いた。 「本当に、僕は君さえいればいいんだよ、リース。」 と。 |
| これだけシリアス。別の短編で書いておりますが、海の妖精だったラルの母親は、ラルの父と契りをかわしたときに妖精としての力すべてを失っています。リースは妖精ではなく精霊ですが、ラルは、自分がリースと一緒になったならリースの力がなくなることを怖れています。予定調和の話にはなるはずなのですが。 |