| 器具の形 | 器具の名前(日本語) | 器具の名前(英語) | 知名度 |
 |
ピペッター (安全ピペッター) |
pipeter(safety pipeter) Peleus Ball for Pipette (Pipettierball ) Safety Pipette Filler 青字は“そらまめ様”からの情報です 有難うございました! 綴りにはドイツ語の影響がある物も多いのですね! |
△ |
| 真面目説明 | 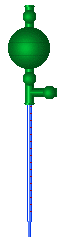 すぐ上にあるホールピペットなどのピペット類を使用するときに、口に薬品を入れる危険を回避するために考案されたゴム製の器具。深緑、青、黒などの色がある。左の図のようにピペット類をしたから差し込んで使用する(左図のピペットはホールピペットではなくメスピペットといわれるものである)。通常の状態では外気と大球との空気流通は行われないが、弁を指で押して歪めることにより流通させることができる。溶液をピペット内に吸い上げるときには、ピペットを嵌めた後、まず上の弁を指で押して歪め、大球を押して大球内の空気を外に出し、その後下の弁を指で押してゆがめる。大球内は陰圧になっているので液が上がってくる。吸い上げた液を落とすときは、分岐の部分の弁を押してゆがめればよい。 すぐ上にあるホールピペットなどのピペット類を使用するときに、口に薬品を入れる危険を回避するために考案されたゴム製の器具。深緑、青、黒などの色がある。左の図のようにピペット類をしたから差し込んで使用する(左図のピペットはホールピペットではなくメスピペットといわれるものである)。通常の状態では外気と大球との空気流通は行われないが、弁を指で押して歪めることにより流通させることができる。溶液をピペット内に吸い上げるときには、ピペットを嵌めた後、まず上の弁を指で押して歪め、大球を押して大球内の空気を外に出し、その後下の弁を指で押してゆがめる。大球内は陰圧になっているので液が上がってくる。吸い上げた液を落とすときは、分岐の部分の弁を押してゆがめればよい。 |
||
| 管理人語り | はい、これを「大ダコ」と呼んでおりました。(因みに「タコ」は駒込ピペットのゴムの部分です)ピペッターを初めて使わせて貰ったのは大学1年生の時、 「口にはいったらどえらいことになる」 と言われた液をホールピペットではかったときです。ああ、こんなに便利なものがあるのなら初めから使わせて欲しかったなあと思いましたですよ。面白いので空気を入れたり出したりして遊んだこともありましたっけ。 これで苦労したことは1つだけ・・・・・ “いい気になって吸い上げて大球の中に液体を入れてしまったときの対処法” ・・・・・・・・・・これやっちゃうと出ないんですよ・・・・・・・普通のピペットのタコより構造が複雑で・・・・・熱するわけにもいかないし、裏返すこともできないし・・・・も、もしピペッターの中から液体を出す良い方法を知っていらっしゃる方がありましたら教えて下さい。・・・・・・・実は職場に1個、やっちゃったのが転がっているのです・・・・・・(涙) |
||
| 器具の形 | 器具の名前(日本語) | 器具の名前(英語) | 知名度 |
| 融点測定装置 | melting-point apparatus | × | |
| 真面目説明 |  固体が液体になるときの温度(融点=melting point)を測定するときに使用する器具。内部に試料をあたためるための液体を入れ、上部の口に温度計を通した栓をつけ、サイド口から、端を閉じた内直径1〜2mm程度の細管につめた試料を温度計の球部を接触するようにしてセットする。(左図参照)試料が溶けた温度を記録する。 固体が液体になるときの温度(融点=melting point)を測定するときに使用する器具。内部に試料をあたためるための液体を入れ、上部の口に温度計を通した栓をつけ、サイド口から、端を閉じた内直径1〜2mm程度の細管につめた試料を温度計の球部を接触するようにしてセットする。(左図参照)試料が溶けた温度を記録する。 |
||
| 管理人語り | 取り扱ったことがない人には「なんじゃこれ?」という器具なのでしょうね。管理人は何度かお世話になりました。有機化合物を同定するとき、融点を測定します。融点がわかればそれが何であるかということがわかりますし、一気に融解しなければ、純品ではなく、不純物が多いのではないか、という推測もたてられます。中に入れる液体は・・・・・・水だと100℃以上の融点のものに対応できないので、濃硫酸、グリセリン、流動パラフィン(液体のろうだと思ってくださいませ)などを使いました。ずっと使っていると硫酸は真っ黒に・・・・・くわばらくわばら・・・・ この実験の何が大変かというと、試料入りの細管を作るところです。内径が小さすぎると試料粉末が入れられないので、ガラス細工で作り直すこと数回。そして、試料をつめるのがまた大仕事。少しでも湿っていると誤差が大きくなるので、素焼き版の上に試料を置き、ミクロスパーテルでこすって水気を取り去りつつ微細粉末にし、細管に詰め、とんとん上下に振って下まで落とす・・・・・・・・・書くとたいしたことがないような感じですが、コレ、無闇に時間がかかるんですよ(そ、それとも私だけですか?)なおかつ、素焼き板上でキシキシやってると、出来た粉が試料の粉なのだか、素焼き板くずなのだか判然としなくなってきます。そして、最後の最後で細管が短すぎたため、濃硫酸の中に水没(硫酸没?)して一巻の終わりになったり・・・・・ 実際、正式な融点測定ってまだこの方法なんでしょうか。この方法ではかった数値が理化学辞典に載っているんでしょうか???・・・・・・・だとしたらきっと『融点測定のプロ』とでもいうべき御方がいらっしゃるのでしょうね。・・・・・・・・細管つくるのに15秒。試料つめるのに10秒。細管セットに5秒。・・・・・・・いらっしゃるのでしたらお会いしたいです。(そしてこの器具を買ってもっていってどてっぱらにマジックでサインをしてもらうのです) ↑追記:大学院に入学した大学で、液体を使わない電気加熱式の測定装置を使用しました。・・・やっぱりずっと楽なものがかなり以前からあるのですね。 |
||
| 器具の形 | 器具の名前(日本語) | 器具の名前(英語) | 知名度 |
 |
スパーテル(スパチュラ) | spatula | △ |
| 真面目説明 |  直訳すれば「へら」。両端がへらになっているものと、左図のように片方が薬さじになっているものとがある。上述のように融点測定管に試料を詰める時や、赤外線吸収の試料を練って調製するときに使う。通常ステンレス製だが、テフロンなどの樹脂でできたものもある。(有機過酸化物を扱う時には金属が薬品分解の触媒となるため、樹脂製を使用する)特に大きさの小さなものを「ミクロスパーテル」という。スパーテルはドイツ語だが、慣例的によく使われている。 直訳すれば「へら」。両端がへらになっているものと、左図のように片方が薬さじになっているものとがある。上述のように融点測定管に試料を詰める時や、赤外線吸収の試料を練って調製するときに使う。通常ステンレス製だが、テフロンなどの樹脂でできたものもある。(有機過酸化物を扱う時には金属が薬品分解の触媒となるため、樹脂製を使用する)特に大きさの小さなものを「ミクロスパーテル」という。スパーテルはドイツ語だが、慣例的によく使われている。 |
||
| 管理人語り | 私の場合、両端ともへらになっているものはあまり使ったことがなかったので、片方が薬さじになっているもののことをスパーテルというのだと誤解していましたが、要は「へら」ってことですね。内科のお医者さんが喉を見て「あ〜、っていってごらん」というときに舌を押し下げる時に使うのもスパーテル。解剖実験のときに内臓を押えるのに使う少し形状の違ったものもスパーテルというそうです。真面目説明でも書きましたように、素材はステンレスのことが多いですが、昔々は「鯨」を使っていたことがある模様。ヒゲでしょうか、骨でしょうか。どちらにしても、現在の鯨をとりまく状況からすればとんでもない貴重品ということになりますね。小さなミクロスパーテルを使うことが多かったのですが、長さ20cm超級のものも存在することは存在し、肩凝るとそれで肩叩いたりしちゃったこともありました(←通常は木槌使用、あれはよく効きます)。ミクロスパーテルで薬さじ付きの場合、薬さじ部分は耳掻きとしても使えそう・・・・・・・・私はやったことはありませんが、なんだか本当に使った人がありそうでちょっと怖いです。・・・と、思っておりましたが、使用報告を複数の方から頂きました!(びっくり)そうですか、結構使えるものなのですね!情報ありがとうございましたv また、SDS−PAGE電気泳動実施後、ゲルを枠から外す(切り出す)際にも使用するとのこと。・・・・そういえば私もやったことがあるかもしれません。(←ああ、健忘症) |
||
| 器具の形 | 器具の名前(日本語) | 器具の名前(英語) | 知名度 |
 |
クランプ(支持器具) | clamp | ○ |
| 真面目説明 |   基本的に、「しめつけて保持する」ための金具。ネジを有するものが多いが、クリップタイプのものもある。狭義ではスタンドに試験管やフラスコなどの器具を設置固定するための金具と考えてよい。金属のままではガラス器具が脱落しやすいので、締め付ける部分にゴムのカバーがされている(左図の青い部分)右図はリング(支持環)といい、金網を載せて丸底フラスコを加熱したり、分液ろうとを静置するときに使用する。その他にも「つり棒」「湯浴用クランプ」「セパラブルフラスコ用クランプ」など用途に応じて様々な形のクランプがある。 基本的に、「しめつけて保持する」ための金具。ネジを有するものが多いが、クリップタイプのものもある。狭義ではスタンドに試験管やフラスコなどの器具を設置固定するための金具と考えてよい。金属のままではガラス器具が脱落しやすいので、締め付ける部分にゴムのカバーがされている(左図の青い部分)右図はリング(支持環)といい、金網を載せて丸底フラスコを加熱したり、分液ろうとを静置するときに使用する。その他にも「つり棒」「湯浴用クランプ」「セパラブルフラスコ用クランプ」など用途に応じて様々な形のクランプがある。 |
||
| 管理人語り | 少し前まで化学畑でない人に「クランプ」というと「CCさくら?」などといわれましたが、今は「ツバサ」でしょうか。意外に知名度低いですね。皆、中学校で必ずといってよいほど触れているものなのですが・・・・・ ゴムカバーですが、アイコンを貸して下さっているkye様も仰っていましたが、しばらくすると、駄目になります。脱落したり過熱でこげたり・・・・・・・・そのときには新しいゴムカバーをかぶせるのだそうですね。・・・・伝聞形なのは、私はこのパターンのクランプを大学では使用したことがないのです・・・・・ゴムカバーなんてはじめっからなかったですよ・・・・・・・・ゴムではなく包帯やぼろ布がぐるぐる巻きにされてましたッ!ぼろ布はよく燃えましたッ!・・・・・・予算がなかったんですよね、しくしく。ろうと台が見当たらないときには、試験管用のクランプで代用などという妙なこともしていたような気がしますし、明らかに固定具のネジとスタンドの心棒の直径が合わないこともありましたっけ・・・。先日某巨大有名大にお邪魔したとき、実験室を見る機会があったのですが・・・・・・・ゴムカバーがかかり、安定もよさそうなずらりと並んだクランプに思わず涙が出そうになりました。・・・・・母校生よ。強く生きて下さい。(統廃合されないことを祈るばかりです・・・・・) |
||
| 器具の形 | 器具の名前(日本語) | 器具の名前(英語) | 知名度 |
| 湯浴(電気調節) | water bath | × | |
| 真面目説明 | |||
| 管理人語り | 銅製鍋による湯煎は80℃とか60℃に保つ場合もありますが、この手のヒーターによる湯煎の場合、管理人はわりに低い温度(40℃前後)でやってました。扱っていたものが、酵素やそれに近いものだったので、動物の体温付近に保つことが多かったためです。・・・・・・・・それにも関わらず沸騰寸前までもっていったこともありますが(血球凝集素を90℃まで加熱し、それでも活性が消えなかったと報告したら、教授先生に「それは何かの間違いだろう」と一蹴されてしまいました)・・・。これよりもっと大きく、試験管たてごと試験管をあたためることができる装置もあります。・・・・4人同時にフットバスとしてできそうなものもあり、ウサギを10匹同時に風呂にいれられそうな巨大なものもありました。風呂・・・・まさに風呂。超小型試験管をあたためるとき、溺れさせてしまったことが幾度かありましたが、酵素系やっているところでは結構よくある光景でしょうか。 | ||
目次に戻る





